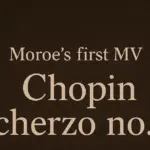(※今日の記事を音声で楽しみたい方はコチラ↓)
https://stand.fm/episodes/691bae3fc8976acc0ee4c926
最近、ライブエンターテインメントの未来について考える時間が多くなった。
ピアノを弾き、教え、ライブを作り、アーティストをマネジメントする僕にとって、このテーマは避けて通れない。
世の中には膨大なコンテンツが溢れ、技術的な“上手さ”だけでは差別化しづらい時代になった。
特にAIが演奏さえシミュレーションしてくる今、「ただ演奏が上手い」はもはや守りきれない一線になりはじめている。
じゃあ、僕たちのライブはどこに価値をつくるべきなのか。
その答えのヒントが、「弾くのではなく、弾かせる」という考え方だった。
■ 観客を“観客のまま”にしない
最近のイベントを振り返っても、心が震えるのは「見せられた瞬間」ではなく、「参加した瞬間」だった。
ピアノでもそうだと思う。
“すごい演奏”を聴いて感動することはもちろんあるけれど、
“自分も音を出した”という体験には、勝てない。
ライブの価値が「鑑賞」から「共創」に移りつつある。
そして、AIが苦手なのはまさにここだ。
観客の呼吸や温度を読み、巻き込み、ひとつの空間を一緒につくること。
それは僕たち人間が持つ固有の力だ。
■ 僕のイベントでも「役割」を設計する
12月13日に予定している『発表会イベント』がまさにそれ。
これからは、観客に“役割”を配るライブが必要になる。
● お客さんが主役
● どんなに初心者であっても参加できるような設計をする
● その人が間違えて止まってしまったら、会場全体で拍手や「ガヤガヤ」を作り出し、アシストする
● 手拍子、歓声などをデザインする
● 勇気を出して演奏した人を、乾杯で称える
● 「次は私も・・・」というモチベーションを作り出す
小さな参加でもいい。
「自分もこのライブの一部だった」と思える仕掛けを、毎回必ず入れたい。
参加・共創・体験には、ある共通点がある。
それは、観客が“身体を使っている”ことだ。
声を出して歌う。
手を動かしてリズムを刻む。
体を揺らす、などなど。
これらをまずは『発表会イベント』でデザインし、いずれはライブイベントでも同じような設計を試みる。
こうした工夫が、AI に代替されないライブを作る。
■ 「見る」から「関わる」へ。フリージョイのエンタメはそこに進む。
フリージョイはアーティストのマネジメントカンパニーだけど、
僕たちが本当に提供したいのは“参加できる体験”だ。
● ただ聴くライブではなく、一緒につくるライブ
● ただ鑑賞する絵本ではなく、物語に入り込む絵本ライブ
● ただ指導されるレッスンではなく、自分で考える
● ただ応援するアーティストではなく、共に世界を広げるアーティスト
そのために必要なのは、
「弾く(見せる)」ではなく、「弾かせる(巻き込む)」という姿勢だ。
これから作るコンテンツ全てに、“役割”と“一体感”を設計していきたい。
■ 最終目標は「涙」
人が泣くのは、
上手さではなく“つながり”に触れた時だ。
そして、今の時代が一番渇いているのは、この「一緒につくる」という感覚。
僕はピアノライブでも、絵本ライブでも、子ども向けイベントでも、
そしてフリージョイ全体の企画でも、
参加者が「自分が必要とされた」と感じられる場を作りたい。
その時間こそが、AIには作れない。
そして僕が作りたい、“涙の時間”だ。
▼音楽教室生徒・講師募集中!
サウンドフリージョイのレッスンを体験してみませんか?
固定のカリキュラムが存在しない、自由に自分のペースで進められる教室です。
ピアノ、ボイトレ、トランペット、ホルン、クラリネット、作曲、編曲などのレッスンが受講可能!
https://sound-freejoy.com/lesson
詳細はこちらのリンクから↓
また、一緒にお仕事ができる講師の方も募集しております。
詳しくはこちら↓
https://sound-freejoy.com/2279
\公式LINEができました/
▼サウンドフリージョイ 公式LINEはコチラ↓